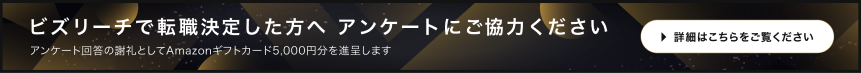東京都国立市、熊本県人吉市

本ページの求人の募集は終了しました。
本ページの求人は、「プレミアムステージ」をご利用でなくても、
ビズリーチ会員であればどなたでも閲覧、応募が可能です。
公開されるや否や100名超の応募が殺到する求人があります。募集主は、名も知られていないような地方の小さな町。仕事内容は、国や全国の自治体から注目を集める、「ビズモデル」と呼ばれる中小企業のコンサルティング。「強みを見いだし、お金をかけることなく、『知恵』で流れを変える」。その手法に再現性があることから全国へと広がっています。そして今、その募集にいわゆるエグゼクティブといわれる人たちがこぞって手を挙げています。彼らはなぜ、自らの地位を捨ててまで、そして移住をしてまで地方に飛び込むのか。現在、実際にその仕事に取り組む3名にお話を伺いました。
募集期間:2021年4月14日(水)〜 2021年5月11日(火)プロフィール
プロフィール

岡崎ビジネスサポートセンター オカビズ 副センター長 高嶋 舞 2002年、第4回にっぽんど真ん中祭り実行委員長(観客動員102万人)。2006年、産業支援第一人者に弟子入りし、起業および産業支援の道に進む。2009年、ちいさな企業の応援団をコンセプトに独立、2014年法人化。2013年オカビズ開設時に副センター長に就任。2009年度経済産業省地域力連携拠点全国最年少コーディネーター、2011年度より、ぎふ女性経営者懇談会委員、2015年度より、「あいち・ウーマノミクス研究会」委員などの公職を歴任。3児の母。 大垣ビジネスサポートセンターGaki-Biz センター長 正田 嗣文 1980年生まれ。横浜生まれ埼玉県出身。大学卒業後、2003年に株式会社エイチ・アイ・エス(HIS)に入社。都内営業所・本社勤務を経て、スペインではマドリード支店・バルセロナ支店、フランスではパリ支店の責任者を歴任。帰任後、現HIS会長兼社長の澤田秀雄氏が経営者を育てる目的で設立した澤田経営道場に選抜され、2年間の経営プログラムに参加。期間中、ハウステンボスのパーク統括本部副本部長兼イベント部部長としてV字回復の基軸となるオンリーワンのイベント実施をモットーに従事。2018年7月4日、大垣ビジネスサポートセンターGaki-Bizセンター長に就任。 湯沢市ビジネス支援センターゆざわ-Biz センター長 藤田 敬太 1978年生まれ、東京都出身。一橋大学経済学部卒業後、読売新聞東京本社編集局の地方部および社会部の記者として約10年勤務。その後、半導体専門商社の経営戦略担当役員として、防衛分野への新規参入や小規模のM&Aに携わる。また、産業用カメラ技術商社の代表取締役としては、財務管理や人事、取引先との交渉、新分野参入のための戦略策定等の業務を行った。2015年に地方ゼネコンの海外事業部長として現地法人を設立。2016年からは現地金融機関の外国直接投資部の顧問を兼任。2019年10月1日、湯沢市ビジネス支援センターゆざわ-Bizセンター長に就任。
応募殺到。エグゼクティブが地位を捨てて飛び込む「地域再生」
────就任されるまでの経緯、応募の動機を教えてください。当時のお仕事を辞めてまで取り組もうと思われた理由、また、なぜそのタイミングだったのでしょうか。

正田:前職では旅行代理店のエイチ・アイ・エスに在職していました。そのなかで現職に応募するきっかけとなった出来事が2つあります。ひとつは、駐在先のヨーロッパで「地方の魅力」に出会ったこと。もうひとつは、帰任後、経営者育成プログラム参加時に携わったグループ会社ハウステンボスで「素晴らしいものを持っている中小企業」に出会ったことです。中小企業支援を通して地方の活性化に携わる。現職はまさに、自分自身がキャリアを築くなかで興味を持った「地方」そして「中小企業」にピタッとはまる挑戦だったため、迷うことなく応募しました。 藤田:そのピタッとはまる感覚、よくわかります。私は年齢の割には人より多くの経験をしてきた自負があり、40歳を超えたあたりから、この経験を何かに生かせないかと漠然と考えるようになりました。大学卒業後に新聞社に編集記者職として入社。約10年間働いたのち、転職後に今度は中小企業で会社を経営する側になりました。その後、小さい会社を運営したり、海外で日本の会社の現地法人を立ち上げたりと、おそらく同世代の人たちよりも経験が豊富です。 そんな数々の成功や失敗のなかで培った、事業ノウハウやビジネスモデルの作り方などの経験や知識を、大げさにいえば「何か世のため人のために生かせないか」と考えていたところ、出会ったのがビズモデルでした。まさに私が追い求めていた答えだったため、即応募。タイミングとしては、何か大きく新しい挑戦をするのに、40歳という年齢が気力も体力も知力も充実した年代だったということもあります。
────高嶋さんは岡崎市からのご指名でオカビズの立ち上げに参加されたと伺いました。地域活性化や中小企業支援の仕事に携わるきっかけを教えてください。

高嶋:私の原点は、学生時代に携わった「にっぽんど真ん中祭り(愛知県名古屋市ほか)」です。多くの方の思いに触れ、「こんなに地域のことを考え動いている人がいるんだ」という衝撃を受けるとともに、彼らの力になりたいと感じるようになりました。そして知れば知るほど、地域活性化には「ビジネス」がポイントではないかと感じるようになったんです。地域を全体的にサポートすることも大切な一方で、それ以上に個々のお店がしっかりと強みを見いだし、競争力を持てるようになることが大事。私自身が力をつけ、そして中小企業をサポートし、地域の、そして日本の活力を取り戻したいと思ったのです。
────ご家族やまわりの反応はいかがでしたか。
正田:前職では、旅行業という職務から離れ、澤田経営道場で経営を学ぶプログラムに選抜していただきましたが、同プログラムは「各世界で活躍できる人材を育てる」というミッションのもと、終了後にエイチ・アイ・エスグループにとどまることを条件としていなかったため、快く送り出していただきました。エイチ・アイ・エス創業者である澤田秀雄理事長の懐の深さを感じ、今でも非常に感謝をしています。さらに、退職後も年に一度はお会いする機会を設けていただくなど、つながりを作ってくれている運営事務局のバックアップもあり、恵まれた環境を今でも心強く感じています。 藤田:私は、ゆざわ-Bizに参画する前はベトナムにいたのですが、自分自身のキャリアについてよく話をしていた友人は皆、私が何をやりたくて、どのような仕事につきたいかを理解していたので、私の今回の挑戦に大賛成でした。彼らとは、地方創生や中小企業の活性化をテーマに話していたこともあり、「日本に帰国したら実際に目で見て肌で感じた中小企業支援の様子を教えてほしい」と送り出されました。 もちろん反対した人もいますが、決断に至った一番の理由は、自分のなかの仕事に対する納得感が一番大きいと思います。秋田県はほとんど行ったことがない県でしたし、まして湯沢市には一度も行ったことがありませんでした。しかし、もともと新たな土地で暮らすのが好きだったこともあり、実際に湯沢市で働いてみて今は毎日が新鮮です。
────100名を超える応募者のなかから採用されたと伺いました。ご自身で評価されたと思うポイントがあれば教えてください。
正田:ひとつは、ビズモデルを理解していることで再現性の可能性を感じていただけたことではないかと思います。もうひとつは、形のない「旅行」というコンテンツを、相手の要望を対面でヒアリングしながら販売してきたことで培った「提案型のコミュニケーション力」が生かせたのではないかと思います。 藤田:確かに無形商材の提案力は通じるものがありますね。最終審査は、実際の事業者の方々が面接官で、事業を営むにあたっての悩みを私が直接聞きながら、解決策を見つけていくという本番の相談業務さながらの「トライアウト」のような選考でした。私が選ばれた理由は明確で、実際に事業者の強みを見つけ、解決策の提示まで持っていけたことだと思います。また、自分自身が会社を経営する立場にいたことから、事業者の抱える悩みや心理状態が非常によく理解でき、事業者目線での会話ができたことも大きかったように思います。
────研修で学んだこと、印象に残るエピソードがあれば教えてください。
正田:どの相談者の方にも必ずいいところがあると確信し、徹底的に話を聞くことから始まり、実践できる具体的な提案をすることです。その根底には、相談者の方へのリスペクトがあるということと、「自分事」として捉える支援者側の情熱が絶対に必要であると考えることができた貴重な機会でした。 藤田:同感です。相談に来る方々の「強み」を見つけて、それをどう光らせていくかを徹底的に考えていますよね。そのためにはまず、コミュニケーション能力の重要性は強く感じました。どの事業者にも必ず強みがありますが、会話を通して正確に、じっくりと聞き出さなければ強みの発見はできませんし、その先にあるはずの新サービスや新商品の創出にもつながりません。 また、私たちの提案や話題が相談者の「腑に落ちるか」も重要だと学びました。いい提案をしても、実行するのは事業者ご本人。提案が独りよがりになってしまっては本末転倒です。研修で相談に同席させてもらった際、「なぜこの提案をしているのか」を他の業界に照らし合わせ、いかにマーケットのトレンドになっているのか、とてもわかりやすく説明していたのが非常に印象的でした。 高嶋:私たちのサポートの根底には、チャレンジャーへの「リスペクト」があります。「支援家」と呼ばれる方のなかには、「指導」に力を入れる方がいらっしゃいます。また、女性や若者のチャレンジを「女、子どもの遊び」と言ってみたり、これまでにない社会課題を解決する事業を「ビジネスにならない」と切り捨てたりするケースを何度も目の当たりにしてきました。 しかし、本当に商品が売れるかどうかを決めるのはマーケットです。「支援家」が決めることではありません。売れないと思った商品を市場に投入したら売れたというケースも、逆に大手企業が膨大な予算をかけ満を持して投入した商品が売れないということもあります。だから、私たちに彼らのチャレンジを否定する権利はない。これはとても大事なこと。私たちはチャレンジされている起業家、中小事業者を尊敬し、そして今の困りごとが解決し、一歩でも二歩でも進むにはどうしたら良いかをともに考えます。
────他の「ビズ」のセンター長やプロジェクトマネージャーと接していて、共通点や刺激など、感じることはありますか。
正田:自分に厳しく、常に自分たちもアップデートするという姿勢を持っていることが印象的です。各「ビズ」の仲間との勉強会や意見交換があったり、各専門分野で活躍されてきた方ばかりなのでお互いの得意な部分で助け合ったりと、課題に対して解決策を見つけるための本気度や取り組む姿勢は、私自身の大きな刺激になっています。 藤田:皆さん、この仕事に対して非常に前向きで情熱的ですよね。私はそれを、ビズモデルを実行していくうえで、各センターの運営が成功するかどうかのバロメーターのひとつだと考えています。全国各地のビズモデルに携わっている方々は、「自分がやらないで誰がやるんだ」ぐらいの心意気や熱意を持った方々が多いと思いますし、こうした情熱や熱意は、私もゆざわ-Bizのセンター長として非常に刺激になっています。 高嶋:これまで中小企業支援に携わる人には経験や資格が重要視されてきました。しかし、この仕事に必要なのは、「適性」です。「コミュニケーション能力」「ビジネスセンス」「情熱」を持ち合わせた人です。実際にオカビズでは当時33歳、NPO経営者だった経験も資格もない秋元がセンター長に就任し、中小企業支援では珍しい女性の私が32歳で副センター長に就任をしました。さまざまな分野の第一線で活躍してきた方たちが、場所は違えど同じ志を持って地域のために奮闘している。それはとても心強いことですし、これまでの経験やノウハウに触れることはとても学びが深く、刺激が多いです。
────実際、相談の現場で感じていることを教えてください。

正田:リアルに成果が求められる難しさを感じる一方、「売り上げが上がった」など、うれしい言葉をいただくことにやりがいを感じます。最近では、東京インターナショナル・ギフト・ショーにて新商品を披露した板金加工メーカーさんがグランプリを受賞され、東京からわざわざお電話で報告をいただいたときは、自分のことのようにうれしかったですね。また、大垣は行政のみではなく民間企業も、ガキビズへの理解とバックアップがすごいので、地域全体で中小企業を支援するという「生態系」ができているのはとても魅力的です。 藤田:私も、思っていたよりも数倍やりがいのある仕事だと、相談の現場に入って実感しています。ゆざわ-Bizに来る事業者の方々は皆、今よりもよくなろうと考えていて、前向きで、本気です。そして、皆さん、相談の帰り際に「ありがとう」と言われます。これまでの人生で、おそらくこんなにも人から感謝の言葉をかけられた経験はありません。それだけ地域に必要とされている仕事なのだと実感しています。またこうした感謝の言葉が、私が仕事をするうえでのモチベーションにつながり、日々「良質なコンサルティング」を提供するために自己研鑽する原動力になっています。 湯沢市の事業者の方々は、皆さんがいいものをつくり、いいサービスを提供していますし、可能性を感じます。しかし、それがうまく消費者に伝わっていなかったり、事業者自身がそれを「当たり前だから」と言っていたりして、結果的に自信をなくしているケースが多いです。こうしたことを含め、第三者の目線で可能性や強みを再認識してもらい、売り上げアップの方策につなげていくことが必要だと日々感じています。 高嶋:ある水産加工会社が、売り上げが下がったと相談に来られました。お話を聞くなかで、昔ながらの手間暇をかけた製法で味には自信があることがわかりました。そこで、高級なおつまみ缶などのトレンドを捉え、少量にし、おつまみとして売り方を変えることを提案しました。粘り強くオカビズでサポートするなかで、その商品は百貨店や旅館に販路を広げ、かつ業務用卸の販路まで開拓でき、今では「忙しくてなかなかオカビズにも行けないよ」とおっしゃっていただけるほどになりました。 私たちの相談は、どんな相談者の方であってもいつも1時間の一本勝負。じっくりとお話を伺い、今後の事業展開についてご提案するなかで、帰る頃には「私にもやれそう! やってみます」とおっしゃってくださいます。実際に多くの方がすぐに行動してくださり、そして継続的にオカビズを活用するなかで「お客さんが増えました」といううれしい報告をくださいます。オカビズの相談員、スタッフの喜びようといったらありません。この瞬間のやりがいは他で得ることはできないでしょう。 オカビズには、福祉事業者、製造業の方、お子様連れの起業家の方や町の和菓子店の方など、さまざまな業種のたくさんの事業者の方がお越しになります。どの方も、「今よりもよくありたい」と前向きな気持ちです。その姿勢に私がいつも元気や勇気をいただいています。地域にはそんなチャレンジャーがたくさんいて、たくさんの可能性を秘めています。
────コロナ禍の影響下で「ビズ」に求められること、これからの抱負を教えてください。
正田:「お金をかけずに売り上げアップ」の必要性がさらに増していると思います。リスクを取るチャレンジが必要なときもあるでしょう。ただ、コロナ禍の影響下においては、私たちの支援スタイルである、知恵やアイデアを使った提案がより求められていると感じています。まもなく開設から3年を迎えるガキビズは、約1,000の事業者にご利用いただきました。今後は、地域内外の事業者同士のコラボレーションを担ったり、SDGsの推進で世界と目線を合わせられる中小企業となるバックアップをしたりと、先を見据えた売り上げアップの提案もしていきたいと思っています。 藤田:コロナ禍は、新たなサービスや商品を生み出すにあたって、逆にチャンスでもあると思っています。それまで、数年かけてゆっくりと変わってきた消費者の性向やトレンドが、コロナ禍の影響下ではほんの数週間で変化していきます。 中小企業は、「ヒト・モノ・カネ」は大手企業に比べると圧倒的に不利ですが、逆に意思決定機能はシンプルで決断も早いため、行動力とスピードは大企業に絶対勝てます。お金のかからない試みであれば、そのスピード感を生かし、いち早く新サービスや新商品にできるのが中小企業の特長です。 コロナ禍の影響下におけるビジネスチャンスやトレンドの変化を、私たち自身がスピード感を持ってキャッチすれば、相談に来る事業者にとってはチャンスの連続だと思っています。そのために「ビズ」がアンテナを張り続け、世の中のトレンドを見続け、何か新しいアイデアのタネを見つける努力をし続けることが重要です。こうした自己研鑽を絶えず行っていけば、おのずと「ビズ」のコンサルティングのクオリティーは上がり続け、それが事業者の売り上げアップという結果として出てくると感じています。 高嶋:オカビズは年間3,000件弱の相談をアドバイザーたちとともに行っています。長くお待ちいただいている事業者の方がいること、また、まだ成果を実感していただけていない事業者の方がいることも事実です。ストイックに日々精進するなかで、より力をつけ、成果に貪欲に、多くのチャレンジャーの皆さんのお役に立っていきたいと思っています。そして、この「ビズプロジェクト」がこれからもっとたくさんの地域に広がり、疲弊している地域が活性化され、日本中が活性化する。その一端を担っていきたいと思っています。
────応募者へのメッセージをお願いします。
正田:過去のどんな栄光もキャリアも捨てて、新しい挑戦をしたい方、人生を人のためにと思える情熱を持っている方には、やりがいのある仕事だと思います。中小企業が持つ可能性を見つけ、相手の立場になって支援し、事業者の売り上げを伸ばし、地域を活性化させ、元気な日本を地方から一緒に創っていきましょう。 藤田:この仕事をするにあたって大事なことは、ビジネスセンスというのは当たり前で、中小企業の支援にかける熱い思いや、いかに事業者の方々と同じ目線でものごとを考えられるかだと思います。私たちが前向きでなければ事業者も前向きになれませんし、いいサービスや商品は生まれません。各地の「ビズ」は皆、独立で運営されていますが、ビズモデルとして各地のセンター長やプロジェクトマネージャーと横のつながりは多く、同じ志を持った人たちの集まりだといえます。日本の未来を元気にするのは、99.7%を占めるともいわれる中小企業です。ビズモデルを各地で実行することは、日本の経済の活性化につながります。中小企業支援を通して日本の未来を盛り上げようという熱い思いを持った方にはぜひ挑戦していただきたいと思います。 高嶋:このプロジェクトは、どの地域でも展開できる、他にはない地域活性化プロジェクト。地域住民、地域企業の持っている可能性を引き出し、その結果、地域が元気になる。そして、地域に活力が戻ることで、日本全体が元気になるはず。私たちへの一つ一つの相談が未来につながる、そんな大志を一緒に抱き、一緒にチャレンジしましょう!
掲載企業(新着順)

東京都国立市
【年収1200万円】都心から電車で30分!「くにたち」ブランドを守るくにたちビジネスサポートセンターKuni-Bizセンター長東京都国立(くにたち)市は、都心から電車で約30分のところにある、面積わずか8.15平方キロメートル、人口約7万6,000人(2021年3月1日現在)のちいさなまち。市内には一橋大学や東京女子体育大学など教育機関が多く、1952年には都内多摩地区初の「文教地区(※)」に指定。市北部の国立駅周辺には多くのギャラリーや和・洋菓子店、レストランなど個性豊かな店舗が並ぶ一方で、南部には昔ながらの商店や商店街が点在し「文教都市くにたち」としてまちの魅力を高めてきました。 しかし、市内の主要産業である卸・小売業は直近20年で事業者数が大幅に減少。また、最近では国立市自慢の魅力的・個性的な数々の個店がコロナ禍の影響で苦境に立たされています。さらに、今後は人口減少の加速が見込まれているため、このままでは市内産業は衰退の一途をたどることが予想されます。そんな状況に歯止めをかけるために、都内初のビズモデル「くにたちビジネスサポートセンターKuni-Biz」の設置を決めました。「くにたち」のブランドを守り、磨き上げていってくださる方を募集します。 ※文教地区:都市計画法により地方自治体が指定する、教育施設の周囲や通学路に教育上好ましくないとされる業種の進出を規制する地区のこと。

熊本県人吉市
【年収960万円】熊本県・人吉しごとサポートセンターHit-Biz(ヒットビズ)センター長人吉市は、熊本県の南部に位置する九州山地の連山に囲まれた盆地にあり、かつて日本を代表する歴史小説家が「日本でもっとも豊かな隠れ里」と評したほど、豊かな自然と歴史、文化が息づくまちです。鎌倉時代から明治維新までの約700年間を、相良氏という同族の領主が統治した全国的にもめずらしい地域で「日本遺産」にも登録されています。 また、世界が認めた「球磨(くま)焼酎」やSLの代名詞といわれる「SL人吉」、人気アニメの舞台としても知られるなど、観光資源や文化資源にあふれています。 しかし2020年、新型コロナウイルスの感染拡大に加え、7月の熊本豪雨で市街地などが甚大な被害を受け、約1,000社の事業者が被災し、被災事業者の事業の再建や新たなビジネスモデルの構築が課題になっています。 そこで活躍が期待されているのが、2018年に中小企業の売り上げアップや起業支援を目的に開設された「人吉しごとサポートセンターHit-Biz(ヒットビズ)」。2020年度は被災事業者を救済する「マイナスをゼロに」する支援が中心でしたが、2021年度は反転攻勢の年にしていきます。あなたにはセンター長として、コロナ禍の影響下における中小企業の売り上げアップに知恵をしぼる、「ゼロをイチ」にする支援を担っていただきたいと考えています。ただ元に戻すだけでなく、創造的復興を実現するために、ぜひあなたの力を貸してください。