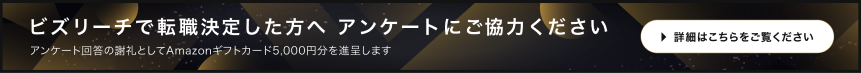厚生労働省

政策立案の司令塔として、人々の生活と国の未来を支える
「ひと、くらし、みらいのために」をキャッチフレーズに、社会保障や労働政策など、人の全てのライフステージと密接に関わる政策をもつ厚生労働省。今回、政策づくりの司令塔として行政の中核を担う「課長補佐級(総合職事務系)」のポジションを募集します。募集の背景と仕事の魅力について、人事課企画官の松本氏と、転職により課長補佐級で入省した2名に伺いました。 ※「募集期間」はビズリーチ上の公募掲載期間です。ページ下部の「確認事項」を必ずご確認ください。
本ページの求人の募集は終了しました。
募集期間:2023年11月14日(火)〜 2023年12月11日(月)
本ページの求人は、「プレミアムステージ」をご利用でなくても、ビズリーチ会員であればどなたでも閲覧、応募が可能です。一人ひとりに寄り添う姿勢とマクロな視点で、日本の課題を解決する

大臣官房 人事課 企画官/松本 直樹 ──はじめに、厚生労働省が掲げているミッションと、主な政策を教えてください。 厚生労働省は、医療や介護、福祉、年金、雇用や労働など、幅広い政策を所掌しています。人生のあらゆるステージに関わる政策を担っていることから、私たちは「ひと、くらし、みらいのために」のキャッチフレーズのもと、全ての国民の一生を支える思いで仕事を進めています。 国民一人ひとりの生活や命に直結する政策に加えて、労働市場政策や、国の一般歳出の5割以上を左右する社会保障制度のように、国全体の盛衰を左右する重要な分野も所管しています。ミクロとマクロ両方の視点から、日本の未来のために取り組むことができるのが、厚生労働省の魅力です。また、高齢化率が世界でも非常に高い水準にある日本の政策は、世界から注目されることも多く、グローバルな課題の解決に貢献することも期待されています。 ──そうした政策を進めるうえで、現在、中途採用を強化する背景を教えてください。 厚生労働省の政策が直面する課題は、価値観やライフスタイルの多様化にも応じて、複雑で多岐にわたるものとなっています。また社会の変化に伴って、行政ニーズは常に変化します。新型コロナウイルス感染症といった新たな感染症への対応や、新しい働き方、技術革新への対応など、前例のない課題とも向き合っていく必要があります。 こうした多種多様な課題を解決していくためには、さまざまな知識、経験、考え方を持つ職員同士で力を合わせていく必要があります。ぜひ、多様なバックグラウンドを持つ方に参画していただき、中核となって活躍していただきたいと考えています。
現場のニーズを政策へ「翻訳」し、世の中を変えていく

──「課長補佐級(総合職事務系)」の具体的な業務内容とキャリアパス、求める人物像を教えてください。 総合職事務系の課長補佐級の職員には、課の司令塔として、法律や予算といった政策の企画立案の中核を担っていただきます。厚生労働省では、特に法令周りに専門性を持つ「事務系」職員のほか、医学・薬学・数理などに専門性を持つ技術職である「技術系」職員、民間や地方自治体などの現場からの出向者も多く働いています。こうしたメンバーと協働しながら、チームのリーダーとして政策を作り上げていく役割が求められます。 係長級の職員は、法律や予算といった政策の企画立案に携わっていただく点は課長補佐級と同様です。チームのなかで、議論に必要な資料作成や調査、調整などを中心的に担っていただくこととなります。いずれも、入省後は厚生・労働といった分野の垣根なく、1~3年おきに、各部局を中心に、場合によっては他省庁や地方自治体、海外の機関などで幅広く経験も積んでいただきます。そして、将来的には省の中核を担う存在になっていただけることを期待しています。 人や社会のために尽力したいという使命感をお持ちで、そのために多くの人を巻き込みながら課題解決ができる方を求めています。業務を遂行するうえでは、論理的思考力や高いコミュニケーション能力も重要です。また、さまざまな領域への広い視野と好奇心をお持ちの方は、よりご活躍いただけると考えています。 ──課長補佐級として働く醍醐味、得られるキャリア価値を教えてください。 現場のニーズを法律・予算などの政策として実現するためには、実現に向けたロジックの構築や、省内外の関係者との調整が必要です。そのなかで課長補佐級の職員は、チームの司令塔の役割を担います。私自身は課長補佐時代、女性や高齢者の就労を後押しする法案や、受動喫煙を防止する法案の作成に携わりました。これらの法律が成立した後には、自分の生活のなかでも世の中が変わったことを実感し、このうえないやりがいを感じました。 業務を通じて、医療・労働など各分野の制度に関する知識を習得できるのはもちろんのこと、多分野の第一人者との人脈を築くこともでき、これらは生涯にわたって自身の財産になると思っています。 ──目指している厚生労働省の将来像、ひいては日本の未来について教えてください。 この世に生を受け、健やかに成長し、大切な人たちとともに、最期の瞬間まで自分らしく生きる。誰もがそんな人生を当たり前に享受できる社会を将来にわたってつくり続けること。それが私の考える、職員一丸となって目指したい日本の未来像です。 厚生労働省の扱う分野は生活に密着しているからこそ、日々の生活で感じたことが生かされる仕事であり、日常を大事に生きることと職業人として成長することがつながっています。経済、財政、地方、国際といった広いスケールのなかで、そのような未来に向けてぜひ一緒に取り組んでいただけたらうれしいです。
銀行から「官」へ。誰もが老後を安心して暮らせる社会を実現する

年金局 企業年金・個人年金課 課長補佐/折口 卓也 ──折口さんは大手銀行から転職され、課長補佐として入省されたそうですが、その経緯や厚生労働省を選んだ決め手を教えてください。 銀行員時代は、融資などの総合的な企業取引のほか、不動産ファイナンスやプロジェクトファイナンスの組成に携わってきました。一人ひとりのお客様からお預かりしたお金を、責任を持って企業の成長や社会インフラの整備等に活用することで、経済の発展に貢献できる非常にやりがいのある仕事でした。 そのなかで、何度か公的機関と連携して行う案件を担当しました。民間の知識や資金も活用しつつ、生活に不可欠な公共サービスを提供する官民連携に将来性を感じ、そうしたプロジェクトに「官」の側から取り組んでみたいと思うようになったのです。 中央省庁のなかでも、厚生労働省は社会保障・労働・医療など所掌が広く、人の生活に密着した制度を担っています。目の前の人に向き合うことを大事にしながら、前職で培った金融の知識や経験も生かし、幅広い行政分野で貢献したいと思ったことが、入省の決め手です。 ──現在の役割と、担当業務についてお教えください。 私は年金局の企業年金・個人年金課で、私的年金制度全般にかかわる仕事をしています。課内の役割としては、課長補佐として、同僚、上司などと連携しながら、政策の立案を担っています。 私的年金制度は、勤務先の企業年金や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」等の個人年金としてなじみのある方が多いかと思いますが、公的年金とは別に保険料を納め、公的年金に上乗せして給付を行う制度です。一人ひとりの自主的な努力によって高齢期の所得保障を充実させる役割を担っているため、より多くの方にご活用いただけるような魅力のある制度とすることが欠かせません。現在は、審議会で専門家の方々に議論していただきながら、現状に即した形での制度の見直しなどを検討しています。
民間で培った「当事者」の視点をもとに、国の仕組みをつくる

──業務を進める中で、特にやりがいを感じる点や、前職でのご経験が生かせている点をお聞かせください。 制度の趣旨を深く考え、その在り方を徹底的に議論できることは行政機関ならではのやりがいだと思います。制度の見直しに向けた議論のなかでも、そもそもの創設の趣旨や目的にまで立ち返り、現行に至るまでの経緯を踏まえて論点を整理しています。単に制度の利便性のみを考えるのではなく、制度を通じて国の仕組みを作るという大きな責任のある仕事に、とてもやりがいを感じています。 また、制度の検討にあたってはさまざまな当事者の視点が必要になります。私は前職で、企業年金を含めた企業取引や、個人取引にも携わっており、企業・個人双方と向き合ってきました。こうした経験は現在、企業や個人が自主的に導入する制度である私的年金制度に関する施策の立案をするうえでも、生かせているのではないかと考えています。 国の行政機関では、個別の企業や個人と取引などを行うことよりも、制度全体を俯瞰することのほうが多いと感じています。ですので、民間企業で制度を実際に活用して仕事をしてきた経験をお持ちの方は、各当事者がどのような点に着眼して行動しているのかという視点をもとに、ご活躍いただけるのではないかと思います。 ──逆に、民間企業から転身されて、業務面や環境面で苦労されたことはありましたか。 最初は、仕事の進め方の緻密さに戸惑いました。例えば民間企業であれば、契約の場面では、効率性や柔軟性の観点から、想定される主要な事象を中心に規定し、発生する可能性の低い事象については「別途協議」といった形で規定することも多いかと思います。しかし、国の制度を考える際には、たとえ発生する可能性が低くても、想定される事象はすべて丁寧に検証し、一つ一つ手当てしていく緻密な仕事が求められます。 はじめは思うように進まないこともありましたが、課内が自由に議論できる雰囲気だったので、根拠が曖昧な点などは都度同僚の助言ももらいつつ取り組んできました。相談しやすい環境があったことが大きな支えになりました。 ──これから厚生労働省で取り組みたいこと、描きたいキャリアを教えてください。 厚生労働省が担当する政策は、社会保障、労働や医療など生活に密着した広い分野にわたっていて、多様な政策に携われるチャンスがあります。また、人の一生のどの時点においても何らかの形で関わりのある、身近な制度が多いことも大きな魅力です。 私は、今後は公的年金も経験しながら年金分野全体の広い知見を得て、誰もが安心して老後を過ごせる社会を作っていきたいと思っています。また将来的にはさまざまな分野で、金融関係の知見も生かしながら、ひとのくらしの向上に貢献していきたいです。
自治体から国へ。現場の思いを、きめ細やかな企画立案に生かす

社会・援護局 保護課 課長補佐/布施 祐希 ──布施さんは地方自治体から転職され、課長補佐として入省されたそうですが、転職の経緯を教えてください。 前職の地方自治体では障がい者福祉行政に長く携わっており、当事者やご家族、関係機関の方々とのやりとりを通じて、個別性の高い課題から地域全体の課題まで、解決に向けて日々実践を重ねてきました。少しずつでも課題が解決していく様を目の当たりにできる地方自治体の仕事は大変やりがいがありました。 他方で、既存の制度では対応できない課題や限界を感じることもあり、地方自治体の枠を超えた広域的な視点での社会保障制度の仕組みづくりにも携わってみたいと思うようになりました。そうした中で、より幅広く国民の生活課題を捉え、その課題解決のために必要な政策の企画立案に携わりたいと思い、厚生労働省への転職を決めました。 ──現在の役割と、担当業務について教えてください。 現在は生活保護制度を所管する社会・援護局保護課に配属されています。生活保護制度は、施行から73年目を迎えるとても歴史のある制度ですが、不断の見直しにより日々進化を続けている制度でもあります。実施機関である地方自治体が制度を運用するためのルールづくりから、定期的な生活保護基準の検証や見直し、医療扶助や各種事業の運用、指導・監査の実施など、さまざまな専門的知見を集約して日々の業務が進められています。 私は課長補佐として、課全体の案件の進捗状況を把握しつつ、各担当係の協力を得ながら政策の企画立案を進める仕事をしています。特に現在は、生活保護制度と生活困窮者自立支援制度の見直しに向けた準備を進めています。実際の業務としては、現状の制度の課題についての省内での議論や、審議会を通じた外部有識者の方の意見のとりまとめなどをリードしています。
チーム体制で、国民の幸せにとことん向き合う

──地方自治体と国の行政機関の違いや、国で働くやりがいを教えてください。 地方自治体と国とでは、政策を企画立案するプロセス自体は大きく変わりません。一方、国は関係者が非常に多いことから、政策のスケールの大きさやスピード感は前職と大きく異なり、正直驚きました。全国各地で日々運用されている生活保護制度をつかさどることは、プレッシャーもある一方、やりがいを感じています。 もう一点、非常にうれしかった驚きは、現場と遠いと思われがちな霞ヶ関が、実は現場によく思いを馳せながら仕事を進めていると知ったことです。出向者の知見で現場感覚を取り入れたり、分からないことは積極的に現場に見聞きしに行ったりと、政策と現場との間に矛盾が生じないかを常に考えながら、きめ細やかな企画立案が行われています。私自身も前職での経験を生かし、政策を実際に運用する地方自治体や事業者などが取り組みやすいものになっているか、現場に混乱は生じないかといった視点を持ちながら話を聞き、意見するよう心がけています。 ──現在の働く環境や、職場の文化についても、お教えください。 私には2人の中高生の子どもがおり、転職を考えた際、子育てとの両立は悩みどころでした。しかし現在は、もう1名の総合職事務系の課長補佐の職員とともに配属され、フォローし合いながら勤務ができています。 その課長補佐も子育て中で時短勤務のため、私が退庁後のフォローをすることもあれば、私が子どもの学校行事等で不在とする際にはカバーしてもらうなどの場面もあります。また、メンターのようにすぐそばで仕事のしかたを教えてもらえる環境があったおかげで、スムーズに職場文化にも慣れることができました。 誰しもが、子育てをはじめ家庭での役割と仕事とを当然に両立できる職場環境の確立は、とても大事なことだと思います。厚生労働省では、時短勤務への理解や、家庭の事情などによる急な休みをフォローできる職場風土があります。「仕事と家庭の両立」に関する施策を所管しているからこそ、職員自身の仕事と家庭の両立についても応援してくれる組織だと感じています。 ──最後に、この記事をご覧の方へメッセージをお願いいたします。 課長補佐の職責には正直プレッシャーも感じますが、とにかく周りの皆さんが助けてくれますし、わからないことは教えてもらえます。大事なことは、シンプルですが、コミュニケーションを積極的に図ることだと思います。 厚生労働省が担う政策は暮らしに直結しており、私たち職員自身も日々その影響を受けているものばかりです。一人の国民としてはもちろん、自治体、事業者などさまざまな立場での「ユーザー視点」も持ちながら、行政官としての専門的な知見を掛け合わせて政策を作り上げるプロセスには、大きなやりがいがあります。多様な意見を取り入れながら、国民の幸せをとことん考えることが大好きな方と、一緒に汗を流して働けることを楽しみにしています。
確認事項
※選考申し込みには、応募書類の提出が必須となっており、以下の通り締め切りがあります。 <2023年度 厚生労働省選考採用試験 応募書類受付期間> ●2023年11月8日(水)~12月14日(木)23:59 ※応募書類などの詳細は、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
募集職種
- 課長補佐級(総合職 事務系相当)/厚生労働行政の政策立案を司令塔として担う
事業企画・事業統括新規事業企画・事業開発リサーチャー・調査員
東京都
【募集背景】 厚生労働省は、「ひと、くらし、みらいのために」のキャッチフレーズのもと、医療、介護、福祉、社会保険、雇用といった、全てのライフステージに関わる政策分野を担っています。 一方、厚生労働省の政策が直面する課題は、価値観やライフスタイルの多様化にも応じて、複雑で多岐にわたるものとなっています。また、新型コロナウイルス感染症といった新たな感染症への対応や、新しい働き方、技術革新への対応など社会情勢の変化に伴い、厚生労働省に期待される役割も大きくなっている中で、民間企業など様々なフィールドでご経験を積んだ多様なバックグラウンドをお持ちの方に、中核となってご活躍いただきたいと考えています。 【業務内容】 ・政策の企画・立案業務 └担当分野にて、現場のニーズをくみながら、課題解決のため法律や予算といった政策を企画立案いただきます。具体的には課の司令塔として、各政策領域の課題分析から対策の検討、そのロジックの構築、省内外の関係者との調整などを主体的に担っていただきます。 ・チームマネジメント └チームのリーダーとして、部下の育成やマネジメントもご担当いただきます。 <担当政策の例> 以下はあくまでも一例です。このほかにも領域横断的な政策も含め、多数の行政課題と分野があります。 ①医療分野 └医療環境・体制の整備、医薬品・医療機器産業の強化、医療DXの推進、予防・健康づくり、生活習慣病・がん対策、生活衛生業の振興、食品の安全確保、医薬品・医療機器の安全確保、薬事規制など ②労働分野 └働き方改革の推進、賃上げに向けた支援、労働条件の改善、高齢者・障害者の活躍促進、外国人の雇用管理、女性活躍、仕事と育児・介護の両立、多様な働き方、企業のキャリア形成・人材育成支援など ③福祉分野 └生活保護、生活困窮者の支援、福祉人材の確保、障害者支援、介護保険、認知症対策、介護現場のICT活用など ④社会保険分野 └医療保険制度、診療報酬・保険適用、医療情報の分析、年金制度、年金積立金の管理運営など ⑤その他 └国際交渉(保健・労働分野)、国際交流・経済連携の推進など <キャリアパス> 入省後は厚生・労働といった分野の垣根なく、1〜3年おきに、各部局を中心に、場合によっては他省庁や地方自治体、海外の機関などで幅広く経験も積んでいただきます。そして、将来的には省の中核を担う存在になっていただけることを期待しています。 【受入体制】 ・具体的な配属先は、これまでのご経験や、能力・適性等を考慮して決定します。 ・各種の研修があるほか、エンゲージメントサーベイや人事担当との面談等により、入省後についてもきめ細やかにサポートします。
- 係長級(総合職 事務系相当)/厚生労働行政の政策立案を支える
事業企画・事業統括新規事業企画・事業開発リサーチャー・調査員
東京都
【募集背景】 厚生労働省は、「ひと、くらし、みらいのために」のキャッチフレーズのもと、医療、介護、福祉、社会保険、雇用といった、全てのライフステージに関わる政策分野を担っています。 一方、厚生労働省の政策が直面する課題は、価値観やライフスタイルの多様化にも応じて、複雑で多岐にわたるものとなっています。また、新型コロナウイルス感染症といった新たな感染症への対応や、新しい働き方、技術革新への対応など社会情勢の変化に伴い、厚生労働省に期待される役割も大きくなっている中で、民間企業など様々なフィールドでご経験を積んだ多様なバックグラウンドをお持ちの方に、中核となってご活躍いただきたいと考えています。 【業務内容】 ・政策の企画・立案業務 担当分野にて、現場のニーズをくみながら、課題解決のため法律や予算といった政策を企画立案いただきます。 その中でも特に、政策実行において議論や調整、それに必要な資料作成や調査などの中心的役割を担っていただきます。 <担当政策の例> 以下はあくまでも一例です。このほかにも領域横断的な政策も含め、多数の行政課題と分野があります。 ①医療分野 └医療環境・体制の整備、医薬品・医療機器産業の強化、医療DXの推進、予防・健康づくり、生活習慣病・がん対策、生活衛生業の振興、食品の安全確保、医薬品・医療機器の安全確保、薬事規制など ②労働分野 └働き方改革の推進、賃上げに向けた支援、労働条件の改善、高齢者・障害者の活躍促進、外国人の雇用管理、女性活躍、仕事と育児・介護の両立、多様な働き方、企業のキャリア形成・人材育成支援など ③福祉分野 └生活保護、生活困窮者の支援、福祉人材の確保、障害者支援、介護保険、認知症対策、介護現場のICT活用など ④社会保険分野 └医療保険制度、診療報酬・保険適用、医療情報の分析、年金制度、年金積立金の管理運営など ⑤その他 └国際交渉(保健・労働分野)、国際交流・経済連携の推進など <キャリアパス> 入省後は厚生・労働といった分野の垣根なく、1〜3年おきに、各部局を中心に、場合によっては他省庁や地方自治体、海外の機関などで幅広く経験も積んでいただきます。そして、将来的には省の中核を担う存在になっていただけることを期待しています。 【受入体制】 ・具体的な配属先は、これまでのご経験や、能力・適性等を考慮して決定します。 ・各種の研修があるほか、エンゲージメントサーベイや人事担当との面談等により、入省後についてもきめ細やかにサポートします。