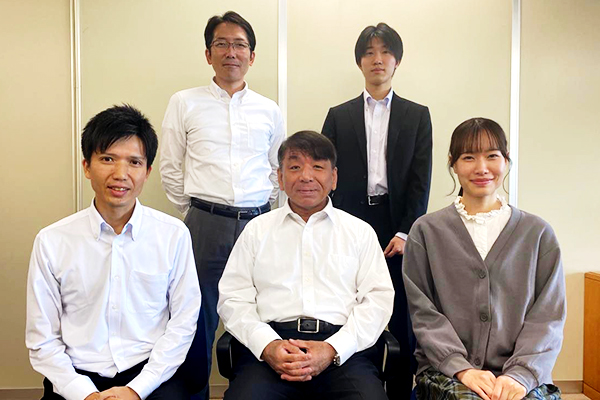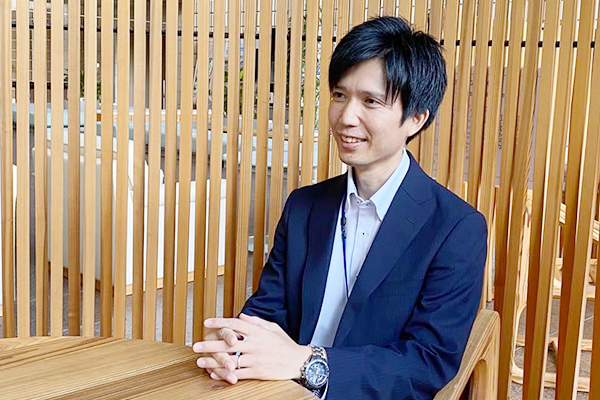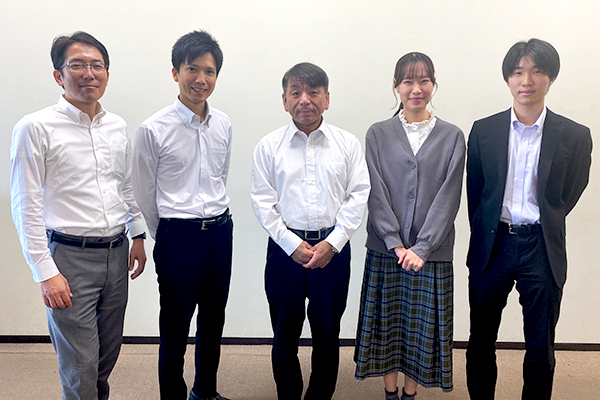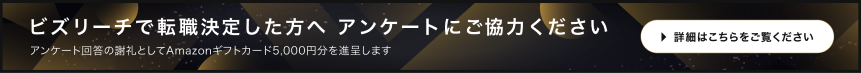福井県

カーボンニュートラル実現へ。地域を巻き込む仕組みづくり
豊かな自然と高い技術力を持つ中小企業を有する福井県は、国の重要課題であるカーボンニュートラルの実現に向け、産学官金民連携のオール福井での取り組みを加速すべく「カーボンニュートラル推進アドバイザー」を副業・兼業として募集します。今回、福井県が目指す姿や同ポジションで働く魅力について、エネルギー環境部エネルギー課長の三寺庄司氏と、昨年から「カーボンニュートラルディレクター」として活躍されている岩井渉氏にお話を伺いました。
本ページの求人の募集は終了しました。
募集期間:2023年11月7日(火)〜 2023年12月4日(月)
本ページの求人は、「プレミアムステージ」をご利用でなくても、ビズリーチ会員であればどなたでも閲覧、応募が可能です。「オール福井」で目指す、カーボンニュートラル実現

エネルギー環境部 エネルギー課長/三寺 庄司 ──福井県では、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、2023年3月に新たな環境基本計画を策定されています。県としてどのような姿を目指されているのでしょうか。 福井県では、2020年7月、福井県長期ビジョンのなかで、「2050年カーボンニュートラルの実現」を宣言しました。2023年3月に策定した福井県環境基本計画では、2030年度の温室効果ガスの排出として、国の目標(46%削減)よりも高い49%削減(2013年度比)を掲げています。 本県は、高い技術力を持つ中小企業が数多くあることや、全国平均より高い森林面積を占める豊かな森林資源を有していることから、脱炭素化のトップランナーとなる可能性を秘めている地域です。これまで温室効果ガスの排出削減は順調に進んでいますが、一方で産業分野において他県と比較し、脱炭素化に向けた具体的な取り組みが十分とは言えません。 2030年までに本県の削減目標(49%削減)に達するには、県内企業・県民一人一人が当事者意識を持って取り組みを強化していく必要がありますが、特に企業では、社会貢献活動の一環という意識が強く、その他さまざまな経営課題と比較すると脱炭素の取り組みの優先順位は高くないのが現状です。そこで、県が主体となって、推進のための土台づくりと脱炭素化への価値づくりを進め「オール福井」で49%削減を目指します。
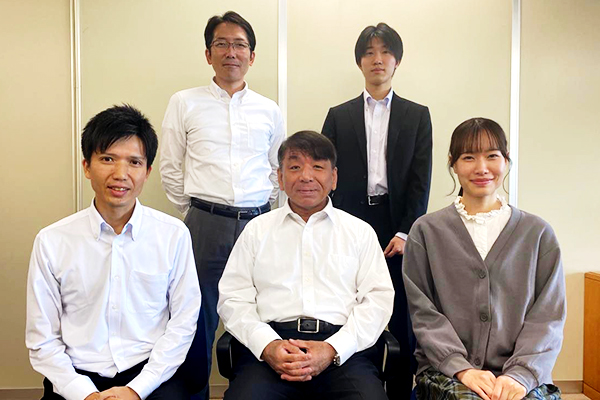
──目標を達成するうえで、今後注力していく取り組みについて教えてください。 カーボンニュートラルを実現するためには、県だけではなく、福井県全体で推進していくことが必要不可欠なため、県や市町、産業界、学術機関などで構成するコンソーシアムを立ち上げ、産学官金民一体で取り組む土台を構築します。 本県では2022年から、DX改革を担ってきた岩井企画主査を「カーボンニュートラルディレクター」に任命し、普及活動に取り組んできました。本年度からはその取り組みを加速させるため、横断的に役割を担っていた機能を集約し、攻めのカーボンニュートラルを推進する「エネルギー環境部」を新設。そして、この11月に産学官金民連携のコンソーシアムを立ち上げる予定です。 具体的には、各界の代表者が参加する全体会議と担当者レベルが参加しテーマ別に行うオープンフォーラムの実施や、コンソーシアムの活動推進のために県と市町の連携会議や全庁での推進本部も立ち上げます。その他、企業表彰や国の機関と連携したセミナーによる意識啓発、ポータルサイトやSNSでの情報発信などにも力を入れていきたいと考えています。 こうした土台づくりと並行して、福井県内の企業や大学等と連携しながら、技術活用やイノベーションによるビジネスチャンスの創出などの価値づくりも行い、事例共有などを通してよいサイクルを回していくことを目指しています。
コンパクトな福井県だからこそ、合意形成を進めやすい

──カーボンニュートラルを目指すなかでの福井県の強みは、何だと思われますか。 福井県は、いわゆる100年企業といわれるような中小規模の老舗企業が多く、家庭的にも三世代同居の比率が高いなど、共同意識や地域連携が非常に強いのが特徴です。そのため、県民や地元企業が一体となって取り組める土壌があることが強みの一つだと思います。コンパクトなコミュニティーだからこそ、顔が見える関係を築けており、関わる関係者が多いカーボンニュートラルのような取り組みも合意形成がしやすいという面があります。 また、地理的には都市部から30分圏内にキャンプ場や海水浴場があるなど、都市部と農村部との距離が非常に近いという特徴があります。このことが環境への意識を高め、経済と自然環境の調和をよいバランスで構築できる県であると考えています。 ──すでにさまざまな体制を構築されているなかで、今回「カーボンニュートラル推進アドバイザー」を副業・兼業で募集する背景について教えてください。 現在は産学官金民連携でのカーボンニュートラルの取り組みを進めるにあたって、各界の課題の違いがあり共通言語がないため、期待通りには連携が進んでいない実態があります。こうした状況を打破するためにカーボンニュートラル推進アドバイザーの方には、ぜひ橋渡しの役目を担っていただきたいと考えています。 また、県民や企業の意識変革がまだまだ必要なので、環境と企業活動の因果関係、環境に関わる世界情勢やビジネス動向、他社事例などの知見をお借りしたいと思っています。私たち行政内部からでは気づきにくい多角的な視点でご助言をいただき、意識改革や行動推進の一助になっていただくことを期待しています。 日本全体の競争力が落ち込んでいる今、カーボンニュートラルの取り組みを一つのビジネスチャンスとして捉えて自社の事業を磨く企業が増えるとともに、県民の暮らしがより豊かになることが、福井県の理想の姿です。そのためにも、今回参画される方に新たな刺激をいただきながら、県庁職員がさらに高い視座と志を持ち、カーボンニュートラルの取り組みを加速していきたいと考えています。
各界と行政の橋渡し役として、社会課題解決の一翼を担う
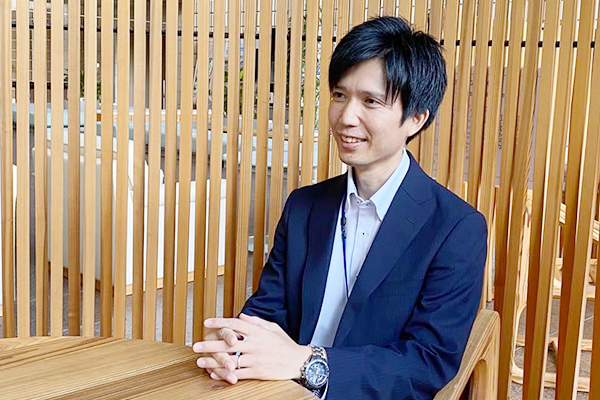
エネルギー環境部 カーボンニュートラルディレクター/岩井 渉 ──カーボンニュートラルディレクターを務める岩井さんの視点から、「カーボンニュートラル推進アドバイザー」に期待する役割、仕事内容を教えてください。 カーボンニュートラルに関する高度な知識や最先端の情報を活用して、県庁や県内の自治体、企業に対してカーボンニュートラル推進への助言をいただきたいと考えています。 具体的には、2024年春以降に運用予定のオープンフォーラムに集まる各企業の課題に対し、解決策を実行・検討するなど、カーボンニュートラルディレクターである私と二人三脚で課題解決に向けて取り組んでいただきます。 産学官金民連携のうち、主にはカーボンニュートラルを進めたいという企業を通しての取り組みを想定していますが、一社一社に相対しアドバイスをいただくというよりも、抽出した課題に対して数社集まるセミナーやワークショップ等を実施する際にご一緒いただくなど、必要に応じて福井県にお越しいただき、現場に入っていただくことも想定しています。 ただ、具体的にお任せする業務は、参画いただく方のご経験や特性に応じてご相談をしていきたいと考えていますので、手段を問わずさまざまなアプローチで福井県のカーボンニュートラル実現を共に目指していただける方を求めています。 ──カーボンニュートラル推進アドバイザーの魅力、この仕事を通して得られるキャリア価値は、どのような点でしょうか。 カーボンニュートラルという国をあげた社会課題を地方行政とともに推進すること自体が大きな魅力だと思います。特に福井県は、産学官金民連携の取り組みを柱としているので、さまざまな業界の方と接しながら、それらをつなぎ合わせる経験は、今後のキャリアにも生かしていただけるはずです。 福井県ではこれまで、未来戦略(長期ビジョン策定)、データ分析、DXと、過去3年にわたりテーマ別に外部アドバイザーのお力を借りて施策を推進してきました。特に民間企業出身のアドバイザーの方々からは、「行政の考え方や目線を知ることができてよかった」「自分が携わった施策が地元メディアに取り上げられ取材を受けるという初めての体験をした」という声を寄せていただきました。また、福井県での経験がきっかけとなり、他自治体からもお仕事のご依頼をいただくなど、ノウハウを横展開して活躍されている方もいるので、行政ならではの経験ができたり、仕事の幅が広がったりなど、チャンスが増えると思います。
組織改編も行い、カーボンニュートラル実現にアクセルを踏む
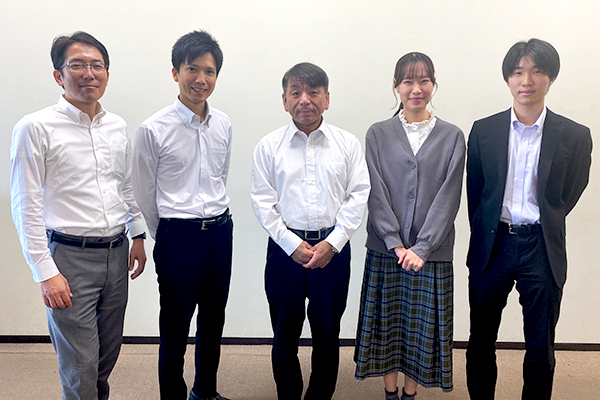
──このタイミングで福井県に携わる面白さ、環境面での魅力について教えてください。 私が着任しているカーボンニュートラルディレクターというポジションは、若手職員に活躍の機会を増やしたいという福井県知事の発想から生まれており、自由な発想や行動力で人と人をつなぐことや新しいアイデアを考えるのが役割です。 行政というと、旧態依然としていて失敗を是としない文化というイメージを持っている方もいるかもしれませんが、本県の知事である杉本は新しいチャレンジを歓迎します。杉本の知事就任以降、前例にとらわれない、前向きで新しい取り組みが増えています。特にエネルギー環境部は若手職員も多くモチベーションの高い組織で、おのおのアイデアを出しあいながら切磋琢磨できる環境だと感じます。 また、副業・兼業での働き方としては、遠方でフルタイム勤務する方にも働きやすいよう、オンライン会議やメール・チャットなどで連絡を取るリモートワーク中心で考えています。例えば、お願いしたい業務が発生するたびに、どのぐらいの時間が必要か、どの程度関わっていただけるかを相談し、稼働時間を決めていきたいと思います。 もちろん、こうした事前の相談も報酬対象になりますし、本業が忙しいときには県の業務は一時的に休み、時間に余裕がある時期に活躍していただくような柔軟な働き方も可能です。作業をお任せするというより、私どもの推進する施策への実際的なアドバイスやノウハウを提供していただくイメージです。 ──「カーボンニュートラル推進アドバイザー」には、どのような人材を求めていますか。経験とマインドの両面でお聞かせください。 目標実現に向けた課題抽出や仮説設定、解決策の提案や助言を期待していますので、さまざまなステークホルダーの意見を聞きながら、一つの目標や課題解決に向けた取り組みをした経験がある方は、その力を存分に発揮していただけると思います。 次いで、業務としての実績は問いませんが「カーボンニュートラルに関する知識をお持ちの方」を求めています。過去を振り返ると、未来戦略(長期ビジョン策定)、データ分析、DXと、テーマ別に外部アドバイザーを採用したときも、民間ならではの豊富な知識や情報で、私たちの知らない部分をカバーしていただけたこと、また、それによって職員の視野が広がりモチベーション向上にもつながったことは大きな成果の一つだったので、今回のポジションの方にも期待しています。 マインド面では、「挑戦」をキーワードに前向きに取り組んでいただける方を求めています。最初は小さな取り組みからのステップになるかもしれないので、一つずつ一緒に考えてくださる方だとうれしいです。関わる方々が「この人の言うことであれば一緒にやってみたい」と思えるような人間力や人を巻き込む力をお持ちの方に、ぜひご応募いただけたらと思います。
募集職種
- 【副業兼業】福井県カーボンニュートラル推進アドバイザー
経営企画・経営戦略戦略コンサルタントマーケティングコンサルタント
福井県
【募集背景】 福井県は、2020年7月に策定した総合計画「福井県長期ビジョン」の中で、2050年のカーボンニュートラル実現を宣言しました。2023年3月に改定した「福井県環境基本計画」の中では、2030年度の温室効果ガス排出量49%削減(2013年度比)という国よりも高い目標を掲げ、取組みを進めているところです。 今年度は特に、カーボンニュートラルに向けた「基盤づくり」に力を入れており、11月には産学官金民連携の「カーボンニュートラル福井コンソーシアム」を設立し、脱炭素化に向けた取り組み方針を決め、「オール福井」でカーボンニュートラルに取り組んでいきます。あわせて、その取り組み方針を推進していくため、ボトムアップでの課題解決を主眼とした、実務担当者による「オープンフォーラム」の運営も予定しています。 このフォーラムでは、企業や団体のカーボンニュートラルに関する具体的な課題を抽出し、課題解決していくことを考えています。企業規模、業種などで抱える課題が多岐にわたることを想定し今後のプロセスをもあえて自由度を高める設計にしています。このように各企業の経営や県民の生活にもしっかりと向き合いながら一つひとつの課題を解決し、オール福井で高い目標をクリアしていきたいと思っています。 とはいえ、これまでカーボンニュートラルの取り組みにおいて私たちだけでは解決し得ない課題も出てきており、本年度から本格始動するこのタイミングでカーボンニュートラル領域のビジネスプロフェッショナルとして、一緒に産学官金民連携を推進していただける方を募集いたします。 【業務内容】 ■「産学官金民連携によるカーボンニュートラル推進」に対する助言、企画の提案 ・コンソーシアム、オープンフォーラムの推進に関する助言、企画〜推進までの伴走 ・県内(庁内・市町・企業等の団体、組織)に向けた脱炭素化に対する助言、研修の企画〜実施 ・福井県の温室効果ガスの削減およびカーボンニュートラルを軸とした「価値づくり」に向けた戦略立案 【得られるキャリア価値】 福井県は人口75万人、市町数も17と非常にコンパクトでまとまりがある県なので、提案・実行したことが福井県全体に浸透していく過程を身近に体感していただくことができます。 また、立ち上げたばかりの産学官金民連携組織の運営に直接携わることで、自身の業務へのフィードバックや新たな人脈の構築や、新たな視点を養うことができます。 【受入体制】 アドバイザーが所属するエネルギー環境部は、今年5月の組織改編で出来たばかりの新しい組織になります。若手職員を中心に活気があり、チャレンジに寛容な職場です。また、昨年4月から庁内外のカーボンニュートラルに向けた調整役であるカーボンニュートラルディレクターと二人三脚で業務を行うことになるかと思います。私ども一同、新しい仲間を迎えることを楽しみにしています。