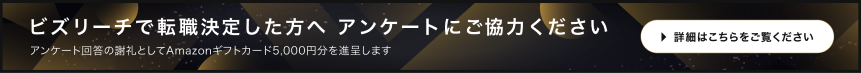独立行政法人国立高等専門学校機構

日本のものづくりを変革する先端教育とは。高専の新たな挑戦
日本の産業の発展と地域活性化を担う技術者の育成を目的として発足した国立高等専門学校(以下、高専)。現場での生きた経験を学生に伝える新たな教育のあり方として「民間副業先生」が注目されています。今回、富山高等専門学校(以下、富山高専)では「AI副業先生」を、全国51の高専を取りまとめる国立高等専門学校機構(以下、国立高専機構)では本部を支える副業・兼業人材を募集します。実現したい未来や求める人物像について富山高専、国立高専機構のキーパーソン3名にお話を伺いました。
本ページの求人の募集は終了しました。
募集期間:2022年12月6日(火)〜 2023年1月2日(月)
本ページの求人は、「プレミアムステージ」をご利用でなくても、ビズリーチ会員であればどなたでも閲覧、応募が可能です。「Society 5.0」時代をリードするAI人材を育成する

富山高等専門学校 准教授/石田 文彦 ──はじめに、富山高専が担っている役割、ミッションについてお聞かせください。 そもそも高専は、日本の産業を発展させる実践的技術者を養成する高等教育機関として、1962年に設立されました。地域産業の発展を担う役割も期待されていたことから、地方都市を中心に開校が進み、現在は全国各地に51校の高専が存在します。 そのなかで富山高専は、工学系学科に加え、商船学科、国際ビジネスといった人文社会系学科も備えている多様性に富んだ学校です。 近年高専では、日本政府が提唱する未来社会のコンセプト「Society 5.0」を実現するための未来技術人材育成事業に注力しています。その一つに、AI・数理データサイエンス、サイバーセキュリティ、ロボット、IoT、半導体などの知識や技術を習得するための次世代基盤技術教育をカリキュラム化する「COMPASS 5.0」というプロジェクトがあるのですが、富山高専はそのなかのAI・数理データサイエンス領域の拠点校の一つに選ばれています。 そこで富山高専は、AI・数理データサイエンスにまつわる教育カリキュラムを強化すべく、今まさに民間企業の現場でAI技術を活用している方に「副業先生」という形でご参画いただきたいと考えています。 ──それが、富山高専が今回募集する「AI副業先生」ですね。なぜビジネス現場で働く人材を求めているのか、もう少し詳しく教えてください。 ここ数年、内閣府がAI戦略としてAI人材育成強化を掲げており、われわれ高専を含め、大学や高等教育機関に対して期待される役割が大きくなっています。また、AI技術は活用の可能性が幅広く、単に知識を詰め込むだけでなく、実際のビジネス現場における知見や活用事例を教育に取り入れることが不可欠です。 高専の専任教員として従事してきたわれわれの知識だけでは、そうした社会の変化やニーズに十分に応えられません。ビジネスの現場でAI技術やその利活用に携わったことのある方の知見をお借りしたいと考え、「AI副業先生」を募集することにしました。 われわれ教員の知識や経験を超える多角的な視点を持ち、より実践的な学びの機会を提供していただけるAI活用人材を求めています。
ビジネス現場におけるAIの生きた知見を、教育に取り入れたい

──「AI副業先生」の具体的な業務内容や、期待する役割について教えてください。 電気制御システム工学科の4年生向け授業の一部をご担当いただきます。さまざまな産業分野でのAI活用事例に触れられる機会を設けたいと考えていますが、授業内容についてはご参画いただく方の得意領域や人数に合わせて柔軟に対応していく所存です。 「AI副業先生」には、担当授業の座学や演習の内容を設計していただくほか、実際の授業では教員としてご登壇いただく予定です。もちろん、われわれ専任教員が教材づくりや学生たちのフォローなどしっかりとサポートをいたしますので、教員経験のない方もご安心ください。 授業や打ち合わせなどは基本的にオンラインで行います。ただし、演習など対面で行うのが最適な授業内容の場合には、富山に足を運んでいただけるとうれしいです。もちろん富山県になじみのない方も大歓迎です。 ──「AI副業先生」として教育に携わる魅力、醍醐味は何だと思われますか。 拠点は富山高専となりますが、「AI副業先生」の授業は単位互換制度を用いて全国51の高専全校での展開を予定しています。全国の教員と連携し、全国の学生とコミュニケーションを取りながら授業を進めていくことになりますので、民間企業での業務とは違った新しい刺激を感じていただけるのではないでしょうか。 また、現代社会においてAI人材育成は急務の課題です。今回募集する「AI副業先生」は、これからの日本の産業を支えるAI人材を育てる重要な役割を担っています。日本の未来を形づくっていく最先端の教育に携われること自体が醍醐味の一つだと思います。 ──「AI副業先生」に求める人物像についてお聞かせください。 必須要件は、ビジネスにおいて何らかの形でAI技術やAIの利活用に携わっていることです。そのうえで、企業研修など指導する側の立場を経験された方を歓迎します。 富山高専は、1学科40人程度の学生に対して教員が10人ほどと、一般的な総合大学に比べると教員比率が非常に高いです。そのため学生と教員の距離が近く、学生の成長を間近で感じられます。大きなポテンシャルを秘めた学生たちに対し、情熱と使命感を持って指導にあたっていただける方にとっては、とてもやりがいのある環境ではないでしょうか。 多様性あふれる富山高専で未来の日本を支えるAI人材を育成したい、という熱意ある方のご応募をお待ちしています。
日本の産業に変革を。デジタル教育とリカレント教育での挑戦
独立行政法人国立高等専門学校機構 教育参事/岸本 誠一 ──国立高専機構では新しく「デジタルものづくりアドバイザー」と「リカレント教育アドバイザー」を募集するそうですが、その経緯をお聞かせください。 国立高専機構では今、「デジタルものづくり教育」と「高度な社会実装教育」の2軸でイノベーションを起こすべく、教育カリキュラムの抜本的な変革を推進しています。 まず「デジタルものづくり教育」に関しては、高専が創設から60年の歴史で培ってきた従来の製造業における実践的スキルを学べるカリキュラムに、最先端のテクノロジー技術を融合させたいと考えています。 製造業の現場ではAIやIoTなどの技術導入が始まっており、例えば仮想空間に製造現場とまったく同じ環境を再現する「デジタルツイン」と呼ばれる技術によって、製造コストの削減が進んでいます。デジタルツインをいかに活用してビジネスにつなげるのか、そういった知見を習得できる教育カリキュラムを新設したいのです。 「高度な社会実装教育」では、地域の社会人に高専で学び直していただくリカレント教育を実施するとともに、高専学生の学びにも還元される仕組みをつくろうとしています。 これらのプロジェクトを推進するのは高専の教員たちですが、民間企業で活躍されている方々に助言やサポートをしていただきたく、「デジタルものづくりアドバイザー」と「リカレント教育アドバイザー」の各ポジションで副業・兼業人材を募集します。 ──それぞれのポジションの具体的な業務内容、期待する役割についてお教えください。 「デジタルものづくりアドバイザー」に期待するのは、ビジネスでの実務経験を生かした、デジタル技術を教育に取り込むうえでのアドバイスです。 先行事例のある企業への訪問同行や高専教員向けの講習会の実施などさまざまな面でサポートしていただきたく、直接的にデジタルツインに触れた経験がなくても、そこにひもづくAI、IoT、5Gといったデジタル技術に関する知見をお持ちの方を求めています。 「リカレント教育アドバイザー」には、地域の社会人に対するリカレント教育の設計や、それを通じた地域活性化や高専学生にも還元される仕組みづくりにご協力いただきます。具体的には、社会人に対する学習ニーズの調査や、集客のための施策立案、協力企業の選定などです。 すなわちリカレント教育の講師ではなく、リカレント教育の枠組みづくりに携わったことのある方を求めています。幅広いステークホルダーとの調整が必要ですので、コミュニケーション力や調整力が必須となるでしょう。地域に関わるプロジェクトマネジメントの経験がある方は、その知見を大いにご活用いただけると思います。 どちらのポジションも、高専の教員が主導するプロジェクトチームと連携しながら、オンライン中心でご参画いただきます。週に数時間程度の業務量を想定していますが、働き方については柔軟に検討しますのでご相談ください。
展開先は全国51校。新たな教育プロジェクトの第一人者になる
──それぞれのポジションの業務を通して得られるキャリア価値や、仕事の醍醐味は何だと思われますか。 「デジタルものづくりアドバイザー」は、最新のデジタル技術を教育に落とし込むことで、これからの日本のものづくりを支えていく非常に重要なポジションです。特にデジタルツインに関しては民間企業でもまだ発展途上の領域ですので、人材育成の先駆者としての経験は今後のキャリアにプラスに働くでしょう。 「リカレント教育アドバイザー」は、学生への教育にとどまらず、地域の社会人の学び直しを支援するポジションです。社会全体の技術力を底上げするというスケールの大きさに醍醐味を感じていただけるのではないでしょうか。 どちらのポジションにも共通するのは、各取り組みがいずれ全国51校に展開されるという点です。日本の教育全体に影響を与えうる、社会貢献度の高いプロジェクトだといえます。 ──さまざまな新しい取り組みを進める国立高専機構ですが、今後の展望や挑戦したい領域などについてお聞かせください。 日々進化していくデジタル技術や、変化する社会ニーズなどを捉えながら、国立高専機構として実践的かつ多様な教育のあり方を実現していきたいと考えています。 イノベーションを起こすための教育改革は、まだ始まったばかりです。15~20歳の可能性にあふれる学生が集まる高専で、ともに新しい教育をつくっていきませんか。
高専の価値ある活動の認知度向上のため、PR戦略をリードする
独立行政法人国立高等専門学校機構 教育総括参事/下田 貞幸 ──国立高専機構では「PRアドバイザー」も募集するそうですが、その背景についてお聞かせください。 これまで国立高専機構では、各高専の活動をWebサイトやプレスリリースなどで発信してきました。しかし専任のPR担当が不在なため、戦略的なPR活動はおろか効果測定も十分にできていません。 われわれ高専では、先端技術を教育に取り込んだり、多様なコンテストを主催したりと先進的な取り組みを進めていますし、地域社会への貢献、海外での活動なども積極的に行っています。 このような価値ある活動も、戦略的なPR活動が不足しているため認知度が低い状況です。もっと多くの人に高専のことを知ってほしい、高専の活動に興味を持ってほしいという思いから、PRアドバイザーとしてご参画いただける副業・兼業人材を募集します。 ──PRアドバイザーの具体的な業務内容や、期待する役割について教えてください。 PRアドバイザーには、高専全体のPR戦略をリードしていただきたいと考えています。対外的なPR活動として、高専への入学促進の観点での中学生とその保護者、中学校教員に向けた発信、地域や政府に向けた発信、そしてメディアとの関係づくりが主な活動になるでしょう。 対内的な活動としては、高専に在籍する教員や学生たちに向けて、高専の魅力をより一層感じてもらえる機会をつくっていただきたいです。いわゆるインナーブランディングですね。 ただし、これらはあくまでも私たちが想定しているものです。実際にご参画いただいた暁には、現状の把握から課題の棚卸し、今後取り組むべき施策の立案からそれぞれの優先順位づけ、そして効果検証まで、PR戦略全体のロードマップをしき、各工程でアドバイスをいただきたいと思っています。 働き方はオンラインを基本とし、ご参画いただける方の要望を伺いながら柔軟に検討します。私たち教員とのやりとりがメインとなりますが、理事長と意見交換をする機会も多くあります。
学生の成長、ひいては社会の発展につながる教育現場の一端を担う
──国立高専機構のPRに携わる魅力や醍醐味はどのようなものだと思われますか。 全国51校ある高専や、それを取りまとめる国立高専機構と、各地域のテーマから社会全体の課題までさまざまな領域に携われるのが魅力です。国立高専機構が主催するイベント、例えば「高専GIRLS SDGs×Technology Contest」などでは、企画段階からご参画いただけるでしょう。 国立高専機構は、「COMPASS 5.0」を筆頭に、日本社会全体が取り組むべき人材育成の課題を解決する大きなミッションを担っています。高専一校一校は、一般的な総合大学に比べて規模が小さいため、そのぶん動きが速く、新しい施策や取り組みをいち早く実施できる体制が整っています。例えば、2022年1月に政府から要請された半導体人材の育成については、わずか数カ月で新たな専門科目を制定し、2022年5月より事業をスタートさせました。 このように高専では、時代や産業の変化に合わせ常に教育をアップデートしています。このスピード感やダイナミズムを広くPRすることに醍醐味ややりがいを感じていただけるのではないでしょうか。 ──求める人物像について、スキルとマインドの両面から教えてください。 スキルや経験としては、PR戦略立案やメディア活用のノウハウをお持ちの方を求めています。教育に関する知見は必須ではないですが、民間企業とは異なった教育機関ならではの文化がありますし、時には文部科学省など政府機関と折衝することもあります。お互いの立場の違いを尊重しながら全体最適を考えられる協調性のある方ですとうれしいです。 ──最後に、この記事をご覧の方にメッセージをお願いします。 われわれは教育機関であって、利益を追求する以上に、学生の成長をより重視しています。教育を通し、学生と社会によりよい未来を残すべく、日々真摯に業務にあたっています。 これからの日本を支える優秀な若き人材を育てる高専の魅力を世の中に広め、日本社会の発展に貢献したいという熱意ある方のご応募をお待ちしています。
募集職種
- <副業・兼業>オンデマンド授業のAI副業先生(富山高専所属)
SE(Web・オープン系)データベースエンジニアデータサイエンティスト
問わず
【募集背景】 当機構は、全国51の高専を束ねており、学生総数5万人の教育を担う、日本最大の国立高等教育機関です。15歳から5年間かけて一貫した技術者教育を行うことに特徴があり、1962年に設置されて以来、高度経済成長を牽引する人材輩出を行い続けてきました。近年では複雑化する社会に技術と知識を用いて課題解決を行う「社会のお医者さん」を輩出することを目指し、Society5.0社会に求められる人材育成を進めてきました。そんな中、内閣府策定「AI戦略」においても、数理・データサイエンス・AI分野について、より一層の教育内容のアップデートが求められており、国や民間企業からの人材輩出への期待は高まりを続けています。 そこで今回、より実社会に即したAI・数理データサイエンスの授業を構築すべく、機構本部とAI・数理データサイエンスの拠点校である富山高専とが連携し、全国の高専のAI授業のブラッシュアップを実施することとなりました。具体的には、「AI戦略」を後押しする取組である文科省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」で求められる要素をもとに、種々の産業分野でのより実社会の現場に即した即戦力を育成できる内容にすることや、これまで各校で行っていたAIに関する授業を要望に応じ、オンデマンド配布する共通授業に置き換えることも検討しています。そのため、既存のAI分野の教員に加え、現役で企業に所属しAI・数理データサイエンス分野で活躍されているビジネスパーソンの経験を求めており、副業先生として協力をお願いできないかと考えました。 AI分野の拠点校となる富山高専では、AIを「掛け算の九九」のような基礎素養として捉えており、多様な学科の学生に履修させるなど、AI・数理データサイエンスの素養を身に付けた人材の育成を重要視しており、早くから学生への教育に取り組んで参りました。富山高専の既存の教育ノウハウに、副業先生の実務的な知見を掛け合わせ、全国の高専を代表するようなAI授業を作ってくださる方の応募を期待しています。 【業務内容】 様々な分野で実社会で活用されるAIを基にしたオンデマンド授業の開発と実施を現職の教員と協力しながら遂行いただきます。 ・カリキュラム準備 ・教材、資料開発 ・オンデマンド授業の製作 ・授業登壇(オンライン・オフラインと必要に応じて) ・その他(卒業研究やAIに関するイベント(DCON出場学生)だけではなく教員等への技術的助言など、適性や希望に合わせて調整します) 【対象授業について】 主に高専4年生を対象にした授業に関する一部を担当いただきます。 既存のカリキュラム(※1)を参考に、ご自身の得意分野の授業を中心に1コマから5コマ程度を担当いただく予定です。面接時に、どの分野のご経験が深いかなどを確認させていただき、柔軟に連携体制を検討していきます。 【期待したいこと】 主にAI・データサイエンスが実社会において、どのように応用されているのか、 そのメリットやデメリット、課題はどういったものなのか、実体験を踏まえて現場のリアルな状況を高専生に教えて欲しいと思います。 ※携わってきた産業により得意分野も異なると思いますので、複数名の副業先生に関わっていただきます。 ※1【参考】既存のカリキュラム概要 授業名:AI・MOT 内容:AIの技術と活用の修得を目指し、AIで使われる技術(機械学習や深層学習)やその活用事例(AIの運用など、実社会での活用の際での留意点)を学びます。合わせて、実データ等を用いた演習、実習により、AIの実活用方法を学びます。 【担当部署】 独立行政法人国立高等専門学校機構 富山高等専門学校(本郷キャンパス) 【得られるキャリア価値】 ・今回作成したオンデマンド授業は全国の高専に広がる可能性が高く、日本のAI・数理データサイエンスの技術者教育基盤を作ることに貢献できる。 ・最先端のAI・数理データサイエンスを学びたいという感度の高い学生に対して、自身の業務経験や知見を教えることで、新たな気づきを得て、技術や経験の棚卸しが期待できます。 ・また、それを持って、高専以外の企業内研修や他大学の教壇などに立つなど、キャリアの広がりも期待できます。 ・多様な高専の教員や副業先生同士のつながりも得ることが可能です。 【受け入れ態勢】 校長、副校長をはじめ、皆様の活躍をサポートする体制を整えたいと考えております。 各担当教員との調整は、富山高等専門学校 准教授の石田がサポートさせていただきます。
- <副業・兼業>デジタルものづくりアドバイザー(本部所属)
新規事業企画・事業開発SE(Web・オープン系)プロジェクトマネージャー(Web・オープン系)
問わず
【募集背景】 当機構は、全国51の高専を束ねており、学生総数5万人の教育を担う、日本最大の国立高等教育機関です。15歳から5年間かけて一貫した技術者教育を行うことに特徴があり、1962年に設置されて以来、高度経済成長を牽引する人材輩出を行い続けてきました。近年では複雑化する社会に技術と知識を用いて課題解決を行う「社会のお医者さん」を輩出することを目指し、Society5.0社会に求められる人材育成を進めてきました。特に現在、ものづくり産業が次々とデジタル化する中で、当機構にもデジタルとものづくりを融合させた実践教育の実施や優秀な人材輩出への期待が高まっております。 そこで今回、デジタルものづくり教育への移行を目標としたプロジェクトチームを新しく立ち上げました。高専では溶接機械、旋盤機械、マシニングセンター等、リアルの現場で使える技術ノウハウや設備が豊富にあるため、今後はデジタルプラットフォームを活用した仮想環境での製品製造にチャレンジできるような環境・カリキュラム制作を行なっていく予定です。先ずは、2高専を対象に進めていき、将来的には全国の高専への展開も視野に入れて活動を行なっていきます。プロジェクトメンバーは有志で集まった経験豊富な教員なため、より実社会に即したノウハウ提供をいただきたく、現役で企業に所属しデジタルものづくりの分野で活躍されているビジネスパーソンの経験を求めており、プロデューサーとして協力をお願いできないかと考えました。 デジタルものづくりは人口減少など社会課題を抱える我が国の解決策の一つとして期待値が高く、間違いなく将来の産業の中心となりうるテクノロジーです。先行事例などを具体化し、プロジェクトを前身させることで、未来のエンジニアたる学生達に啓蒙・教育に繋がっていくことをやりがいに、是非参画いただければ幸いです。 【業務内容】 ・企業(ものづくり現場)におけるデジタル技術の導入事例の調査 ・企業の事例を教育へ導入する際のマネジメントとアドバイス ・プロジェクトチームの目標・組織管理等のサポート 【期待したいこと】 デジタルものづくり(デジタルツイン等)が実社会において、どのように応用されているのか、 そのメリットやデメリット、課題はどういったものなのか、実体験を踏まえて現場のリアルな状況を踏まえて、 プロジェクトメンバーにアドバイスをいただければ幸いです。 【担当部署】 独立行政法人国立高等専門学校機構 本部事務局(東京都八王子市)、リモート可能 ※プロジェクトに応じた新チームを組成予定で、配属はそちらの予定です。 【得られるキャリア価値】 ・最先端のデジタルものづくりに対する自身の業務経験や知見を教えることで、新たな気づきを得て、技術や経験の棚卸しが期待できます。 ・また、それを持って、高専以外の企業内研修や他大学の教壇などに立つなど、キャリアの広がりも期待できます。 ・多様な高専の教員とのつながりも得ることが可能です。 【受け入れ態勢】 機構本部では、皆様の活躍をサポートする体制を整えたいと考えております。 各プロジェクトメンバーとの調整は、本部事務局の学務課及び担当教員がサポートさせていただきます
- <副業・兼業>リカレント教育アドバイザー(本部所属)
新規事業企画・事業開発人材開発・人材育成・研修組織・人事コンサルタント
問わず
【募集背景】 当機構は、全国51の高専を束ねており、学生総数5万人の教育を担う、日本最大の国立高等教育機関です。15歳から5年間かけて一貫した技術者教育を行うことに特徴があり、1962年に設置されて以来、高度経済成長を牽引する人材輩出を行い続けてきました。近年では複雑化する社会に技術と知識を用いて課題解決を行う「社会のお医者さん」を輩出することを目指し、Society5.0社会に求められる人材育成を進めてきました。また、対象は学生だけでなく社会人にも広がってきており、高専は全国各地にあることから、各地域での社会人のリカレントまたはリスキルの学び舎にというニーズも高まっています。 そこで今回、地域の社会人と学生との協働を実現する新しいプロジェクトを立ち上げました。具体的にはリカレント教育を受講する社会人と高専学生とでプロジェクトチームを組成し、新技術を用いたビジネスコンテストを開催する等です。先ずは、5高専を対象に進めていき、将来的には全国の高専への展開も視野に入れて活動を行なっていきます。プロジェクトメンバーは有志で集まった経験豊富な教員ですが、リカレント教育に関する知見や地域との連携やプロジェクト推進に関するノウハウが不足しているため、現在地域連携やコミュニケーション等の分野で活躍されているビジネスパーソンの経験を求めており、プロデューサーとして協力をお願いできないかと考えました。 社会人の方々には「リカレント・リスキル教育」の実施により、新技術の導入や学び直し、また他社会人や教員、学生との協働による新たな人脈の形成等、キャリアの可能性を広げることができます。高専は地元企業へ人材を数多く輩出しており、今後も各地域の産業を支える鍵だと捉えております。主体的にプロジェクトを推進し成功に導くことで、地域そのものを成長させることにやりがいを見出せる方のご応募をお待ちしております。 【業務内容】 リカレント教育のアドバイザーとして、以下業務の遂行をお願い致します。 ・リカレント教育のフレームづくりへのアドバイス ・リカレント教育のノウハウ提供とアドバイス ・プロジェクトチームの目標・組織管理等のサポート 【期待したいこと】 リカレント教育に関する体系的な情報共有や、地元地域との連携・協業、プロジェクトに関与しながら主体的に推進することを期待しております。 【担当部署】 独立行政法人国立高等専門学校機構 本部事務局(東京都八王子市)、リモート可能 ※プロジェクトに応じた新チームを組成予定で、配属はそちらの予定です。 【得られるキャリア価値】 ・リカレント教育や地域連携に対する自身の業務経験や知見を教えることで、新たな気づきを得て、技術や経験の棚卸しが期待できます。 ・また、それを持って、高専以外の企業内研修や他大学の教壇などに立つなど、キャリアの広がりも期待できます。 ・多様な高専の教員とのつながりも得ることが可能です。 【受け入れ態勢】 機構本部では、皆様の活躍をサポートする体制を整えたいと考えております。 各プロジェクトメンバーとの調整は、本部事務局の学務課及び担当教員がサポートさせていただきます。
- <副業・兼業>PRアドバイザー(本部所属)
広報・PR・広告宣伝マーケティングコンサルタントプロデューサー・ディレクター
問わず
【募集背景】 当機構は、全国51の高専を束ねており、学生総数5万人の教育を担う、日本最大の国立高等教育機関です。15歳から5年間かけて一貫した技術者教育を行うことに特徴があり、1962年に設置されて以来、高度経済成長を牽引する人材輩出を行い続けてきました。近年では複雑化する社会に技術と知識を用いて課題解決を行う「社会のお医者さん」を輩出することを目指し、Society5.0社会に求められる人材育成を進めてきました。 しかし、人材育成に関する様々な取り組みを行っているものの、その成果や価値が世の中に伝わっているかというと疑問が出てきます。一部の関係者には知られていますが、高専を目指す中学生やその親世代、高専生が就職する先の企業の方など、世の中に広く知られていないというのが現状です。ともすると、全国の高専同士でも情報が伝わりきっていないこともある状況です。 そこでこの度、価値ある高専のさまざまな取り組みについて「情報発信力」を強化すべく、本部で広報活動を牽引いただける方に副業でのご協力をお願いしたいと考えております。本部は全国の高専を統括しておりますが、大学とは異なり組織としての規模はコンパクトです。そのため、理事とも距離が近くアドバイスいただいたことが組織全体に影響力を持つことが特徴です。これまで当機構では広報業務の先任者がいない状況が続いておりましたので、ご協力いただける副業人材の方には、広報のプロフェッショナルとして、組織に対しても広報とは何かを教えていただくようなことも期待しています。 【業務内容】 PRアドバイザーとして、以下の広報業務をお願い致します。 ・下記にある各ターゲットに対する広報戦略の立案、実行支援 ・プレスリリース、広報資料の企画・作成支援 ・メディアリレーションズ(新聞、テレビ、雑誌 等) (具体的には) 先ずは高専が注力している「Society5.0型未来技術人財」育成事業における次世代基盤技術教育のカリキュラム化「COMPASS 5.0」に関する情報発信についてお願いします。「COMPASS 5.0」とは、これからの技術の高度化に関する羅針盤(COMPASS)と位置付け、高専教育に組み込むことで新たな時代の人材育成機関としての高度化を図るという、当機構ならではな唯一無二の取組で、現在はAI・数理データサイエンス、サイバーセキュリティ、ロボット、IoT、半導体という分野で事業を進めております。 この取り組みを、以下の3つのターゲットに対して広報戦略を立案するところから伴走いただきます。 1)未来の高専生とその親 2)高専生の卒業後に関係する就職先企業 3)「COMPASS 5.0」のノウハウを活用すべき全国の高専教員 4)省庁及び地方自治体等の行政 5)各種産業界 6)教育機関・研究機関 7)金融機関 【担当部署】 独立行政法人国立高等専門学校機構 本部事務局学務課(東京都八王子市)リモートワーク可 【得られるキャリア価値】 ・PRに対する自身の業務経験や知見を教えることで、新たな気づきを得て、技術や経験の棚卸しが期待できます。 ・また、それを持って、高専以外の企業内研修や他大学の教壇などに立つなど、キャリアの広がりも期待できます。 ・多様な高専の教員とのつながりも得ることが可能です。 ・当機構の学生輩出は我が国の社会課題の解決策の一つとして期待値が高く、全国の学生へ影響を与えます。そのスケールの大きさは価値になると思います。 【受け入れ態勢】 機構本部では、皆様の活躍をサポートする体制を整えたいと考えております。 各プロジェクトメンバーとの調整は、本部事務局の学務課及び担当教員がサポートさせていただきます。